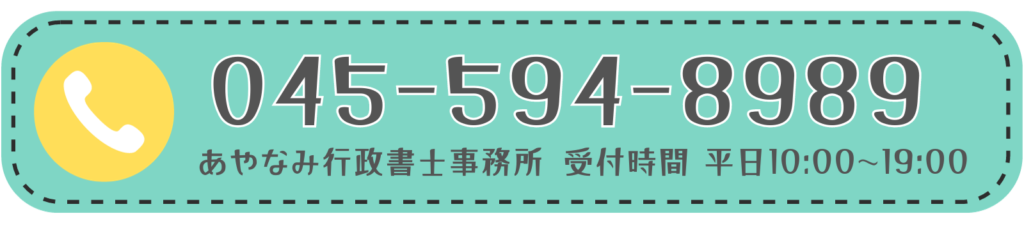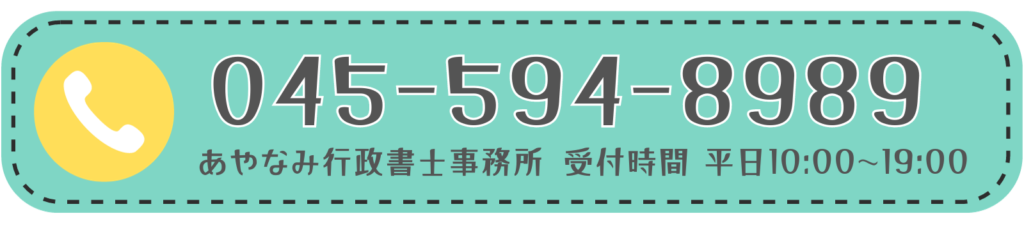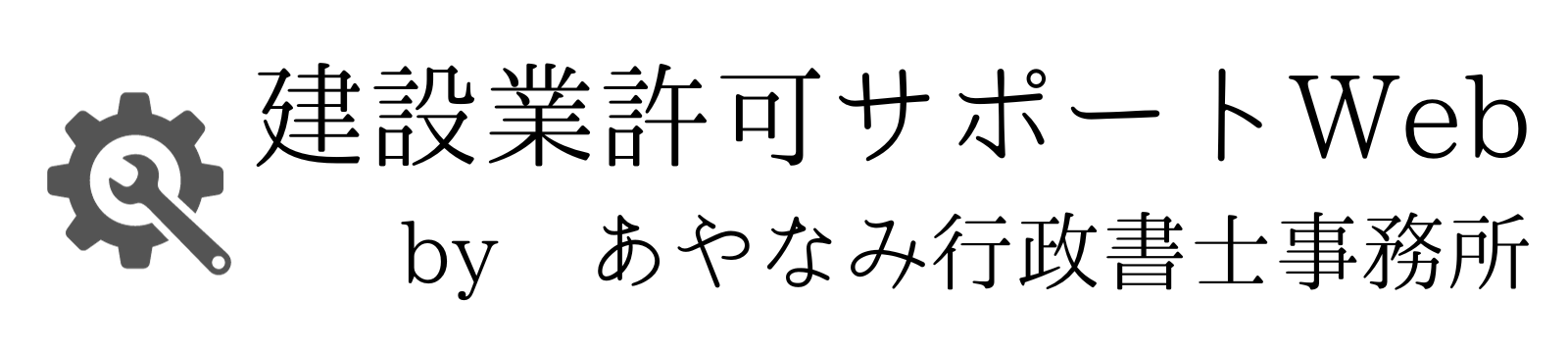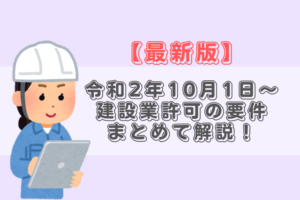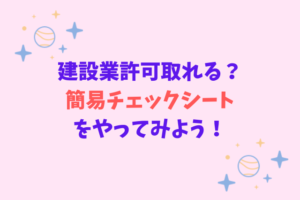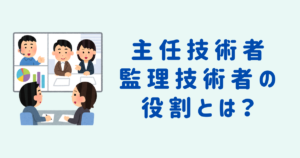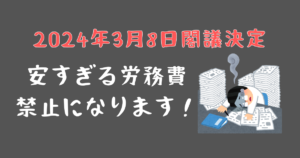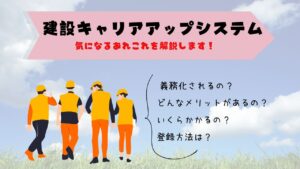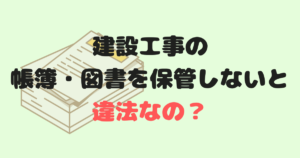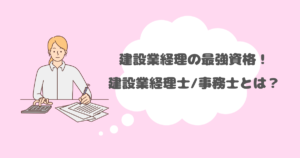行政書士宮城彩奈
行政書士宮城彩奈こんにちは!
行政書士の宮城彩奈(@ayanamiyagi)です。
建設現場には、その会社に所属する主任技術者か監理技術者を配置しなければなりません。
その主任技術者か監理技術者は、所属する会社と「直接的かつ恒常的な雇用関係」がなければなりません。
また、建設業許可の「専任技術者」になっている方は、原則現場に配置される主任技術者か監理技術者になることはできません。※例外はありますが、省略します。
なぜかと言うと「専任技術者」は、営業所に常駐していなければならないからです。
近年、建設業界は人手不足や資格者不足が目立つので、この主任技術者または監理技術者の配置が会社にとってとても負担になる事が非常に多いのです。



現場に配置しなければならない監理技術者と主任技術者が不足しているんだよね。



そんな時は「企業集団確認」という特例が使えるかもしれません。
企業集団確認って何?と思うと思いますが、簡単に言うと「親会社・連結子会社が1つの企業体になってます」という旨を国土交通省に「企業集団確認申請」を行い確認書の交付を受けると、その企業集団の中で監理技術者や主任技術者を出向させることができるという制度です。
ただ、条件や注意点があるのでこれから解説します。
ちなみに、主任技術者や監理技術者の基本知識については以下の記事を参考にしてください。
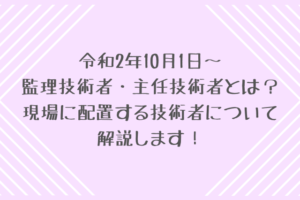
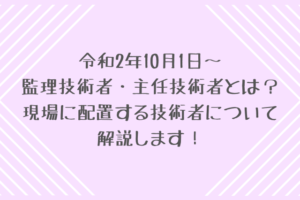
企業集団確認を受けられる条件は?
この「企業集団確認」を受けようとする場合は、当分の間は以下の条件全て国土交通省不動産・建設経済局建設業課長に確認を受けなければなりません。
- 一の親会社と連結子会社からなる企業集団であること。
- 連結子会社が建設業者であること。
- ②の連結子会社が①の企業集団に含まれること。
- 親会社または連結子会社のどちらか一方が経営事項審査を受けていないこと。(連結子会社が2つ以上ある場合は、それら全て。)
- 親会社または子会社が、既に他の企業集団確認の取扱の対象になっていないこと。
- 親会社が次の全てに該当すること。
・建設業者であること。
・有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない、または、会計監査人設置会社であること。



企業集団確認を受けた場合は、出向社員は出向先の建設業者との間に直接的かつ恒常的な雇用関係があるものとして取り扱うことができます。
ただし、出向先の会社が出向社員を主任技術者または監理技術者として置く工事について、その企業集団を構成する親会社、連結子会社、親会社の非連結子会社が、その工事の下請人になる場合は、出向社員を主任技術者または監理技術者に置くことはできません。
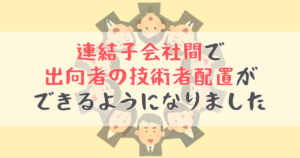
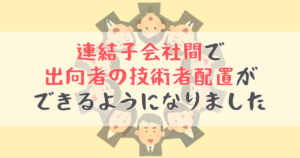
企業集団の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認方法
企業集団確認の取扱では、工事現場等で次の書類によってそれぞれ確認します。
- 健康保険被保険者証で出向元の会社と出向社員の雇用関係を確認。
- 出向であることを証明する書類(出向協定書や出向契約書等)で、出向先の会社と出向社員との雇用関係を確認。
- 企業集団確認書で、出向先の会社と出向元の会社との関係が、企業集団の親会社と連結子会社の関係であることの確認。
- 施工体制台帳等で、出向社員を主任技術者または監理技術者としておく建設工事の下請負人に企業集団に含まれている親会社、連結子会社、親会社の非連結子会社が含まれていないことを確認。
出向可能なパターンとは?
企業集団確認を受けると企業集団の中で、親会社から子会社に出向社員を送ることができます。
子会社は、親会社からの出向社員のみを置くことができ、子会社間の出向は認められません。
※子会社間の出向は、3ヶ月後等配置可能型であれば可能になりました。(2024年4月1日改正)
出向社員を配置した場合は、その工事は企業集団に含まれる連結子会社や非連結子会社が下請に入れなくなります。
発注者から直接工事を請け負った元請がいて、1次下請けに入った子会社に元請から監理技術者等を出向させた場合は、2次下請け以降に企業集団に含まれる関係会社が下請に入れなくなるということです。
これが基本です。
その基本を踏まえて、以下のパターンを簡単に解説します。
子会社から親会社に出向する場合は?
親会社は子会社からの出向社員を置くことができます。
親会社から孫会社へ出向する場合も対象?
親会社から孫会社への出向についても、有価証券報告書や監査を受けた連結決算書で孫会社の確認が取れれば可能です。
親会社が発注者兼元請で、子会社から出向した場合は?
親会社が発注者で元請の場合で、親会社は子会社からの出向社員を置くことができます。
その場合も、出向元の子会社(その他、関係会社含む)はその工事の下請に入れません。



企業集団確認申請の目的は、元々1つの会社だった会社が経営の都合で分社化した時に監理技術者等が足りなくなる問題を解消するために作られたものなのです。
経営事項審査を受けているけど、企業集団内の別の会社に変更したい場合は?
企業集団確認を受けている企業集団内では、親会社または子会社のどちらか一方が経営事項審査を受審できます。
現時点で経営事項審査を受けている子会社から、親会社が経営事項審査を受ける場合は、親会社または子会社どちらか一方に該当するので、親会社が経営事項審査を受けた場合は子会社は経営事項審査を受けることができません。
上記パターンだと親会社が経営事項審査の申請した時点で、親会社と子会社の両方が経営事項審査を受けたと判断されるので企業集団確認は失効してしまいます。
企業集団確認を維持しながら子会社から親会社に経営事項審査を切り替えるベストなタイミングは、子会社の経営事項審査の有効期限が切れた後に親会社が経営事項審査の申請書を提出しましょう。
経営事項審査の有効期限が切れた後、親会社が経営事項審査の結果通知書を受け取るまでは企業集団内で経営事項審査を受けている会社はゼロになります。
公共入札をしている場合は、上記を踏まえて切り替えるタイミングを検討した方がよいでしょう。
経営事項審査を受けることができるのは「親会社または子会社どちらか一方」なので、A子会社からB子会社に経営事項審査を変更する場合と、子会社2社以上が経営事項審査を受ける場合のタイミングはいつでも構いません。
企業集団確認申請の手続きに必要な書類は?
- 親会社が有価証券報告書提出会社の場合は、申請時の親会社・連結子会社・非連結子会社の体制における有価証券報告書の写し。
※ただし、直近の有価証券報告書の作成後に合併等で会社の体制が変更になった場合は、直近の有価証券報告書と会社体制がわかる資料(変更がわかる公表資料、登記簿謄本、有価証券報告書の監査人の確認を受けた書類等)
その場合、新しく有価証券報告書を作成した時は、新しいものの写しを提出する。 - 親会社が有価証券報告書提出会社ではない場合は、会計監査人の監査を受けた事業報告、事業報告時点の連結計算書類等。
※ただし、事業報告と連結計算書類等の作成後に合併等で会社の体制が変更になった場合は、直近の事業報告、連結計算書等、会社体制がわかる資料(変更がわかる公表資料、登記簿謄本、会計監査人の確認を受けた書類等)
その場合、新しく事業報告と連結計算書類等を作成した時は、新しいものの写しを提出する。 - 親会社と連結子会社の建設業許可通知書の写し
許可通知書の内容から変更がある場合は、収受印がある変更届での写しを一緒に出しましょう。
また有価証券報告書に記載がある連結子会社一覧に名前がない場合は、別途一覧を作成して証明しましょう。
また、申請書はその企業集団に所属する全ての会社が承認したものでなければなりません。
申請後、国土交通省不動産・建設経済局建設業課長は申請者に対して企業集団確認書を交付し、有効期間は交付日から3年です。
※確認書の有効期限は1年から3年に変更しました。(2024年4月1日改正)経過措置として、改正前に既に交付済みの確認書については有効期限からさらに2年間有効です。
有効期間内に企業集団確認書の記載事項に変更があった場合は、親会社は国土交通省不動産・建設経済局建設業課に変更内容を報告します。
その変更によって、企業集団の要件を満たさなくなった場合は、変更があった時点で企業集団確認書は無効になります。
変更届はどんな時に必要?
企業集団内で、以下の内容に変更があった場合は届出が必要です。
- 商号
- 所在地
- 許可番号の変更
- 経営事項審査の受審状況
- 建設業許可を受けている会社の状況に変更があった場合
③は、建設業許可を知事許可から大臣許可へ変更した場合や、都道府県をまたいでの所在地の移転だと許可替えの申請が必要になり建設業許可番号が変わる場合があるので③に該当します。
⑤は、企業集団内は建設業許可を持つ全ての連結子会社が企業集団に属してなければならないので、連結子会社のうちに新たに建設業許可を取得した会社ができた場合や、建設業許可を廃業した場合も変更届が必要な事項になります。
まとめ。
企業集団確認制度が使える会社は大企業または中企業くらいの規模になってくると思います。
また、「この場合はどうなの?」など、複雑でいろいろなパターンの疑問が出てきてしまうと思います。
そんな中、行政書士も企業集団確認を扱っている事務所はかなり少ないと思いますが、当事務所は企業集団確認も取扱いが可能です。
本記事が参考になれば幸いです。
建設業許可、経営事項審査等の申請手続きや建設業法令に関するご相談がございましたら、あやなみ行政書士事務所へご相談ください。
- スマートフォンの場合は以下の電話番号ボタンのタップで電話がつながります。
- お問い合わせ内容により、有料相談(30分5,500円)となる場合がございます。
- ご相談前に、会社名・担当者名等をお伺いいたします。