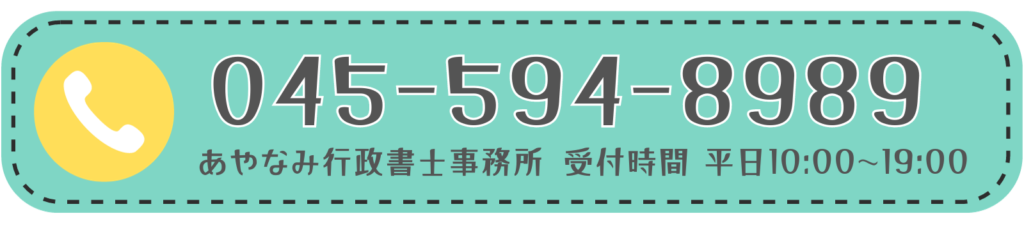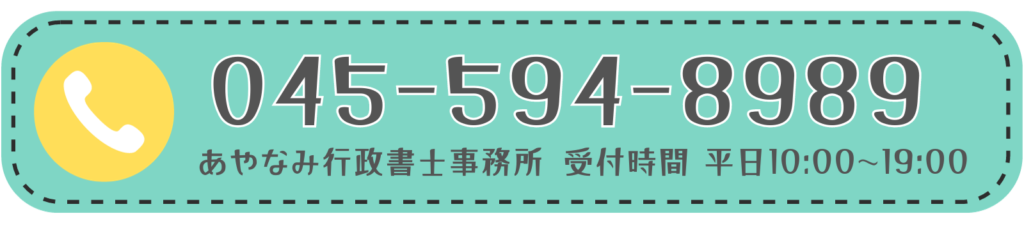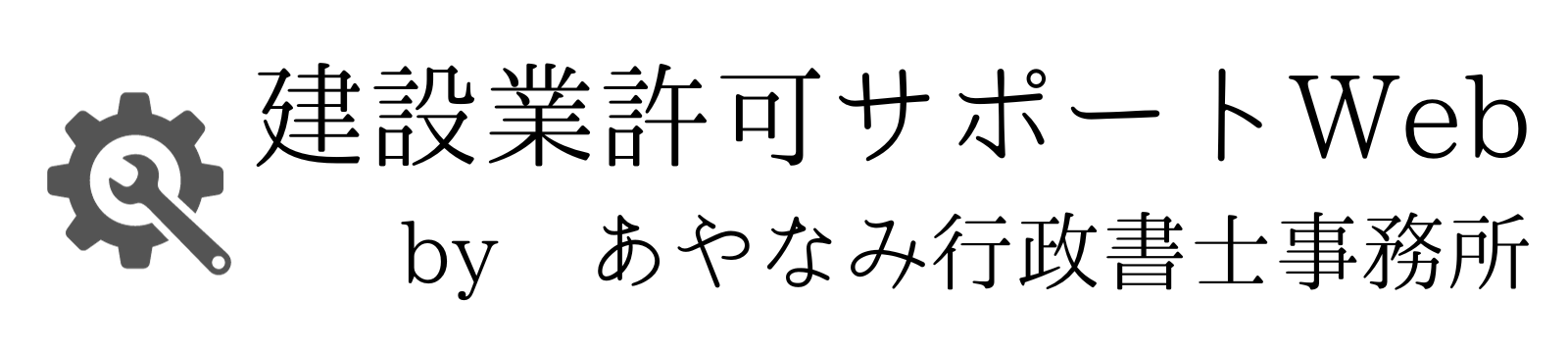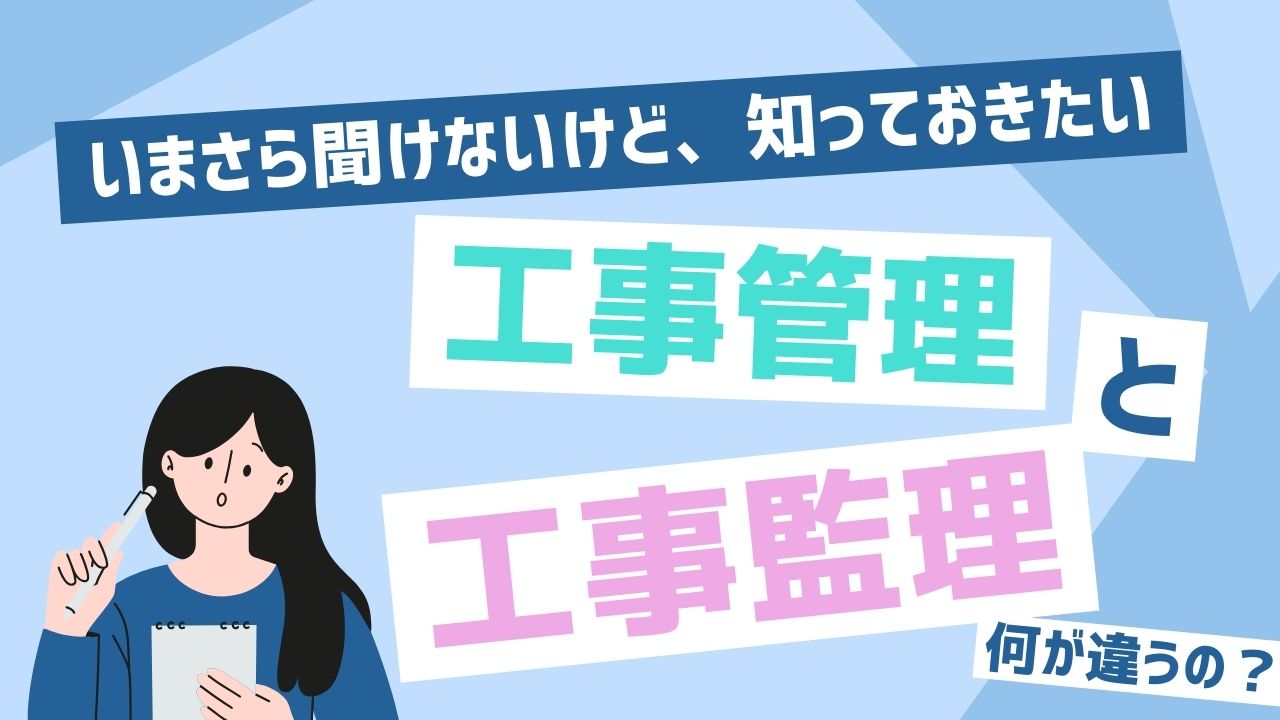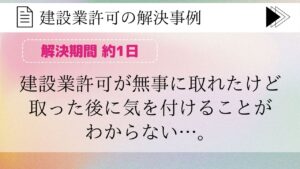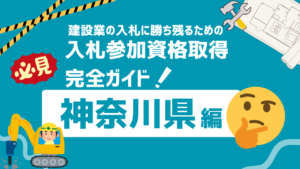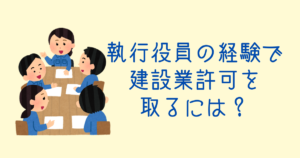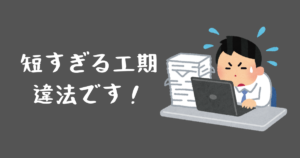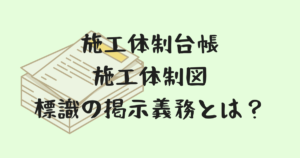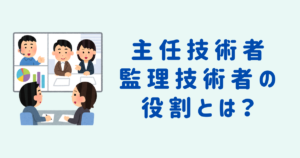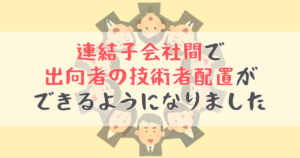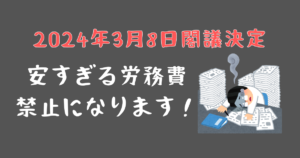ジャスティン
ジャスティン「工事管理」と「工事監理」って違うの?



似ているから間違えやすいけど、実はそれぞれ意味が違うんだ。



知らなかった。建設用語って難しいよね。



「工事管理」は、「施工管理」とも呼ばれているよ!
大丈夫!少しずつ、覚えていこう。
工事管理(施工管理)とは
工事管理(施工管理)とは、工事の施工者(例えば、建設会社や施工業者)が行う作業です。
もっと簡単にいうと、「工事が予定通り進んでいるかどうか」「従業員や現場周囲の安全状態を守れているか」など工事の指揮監督および工事全体を管理する現場監督のことを指します。


なお実際の現場では、資格を所有していない「現場監督」がいます。
これは、違法というわけではなく、資格の有無と業務範囲によって工事管理(施工管理)と区別されているのです。
資格を所有していない場合は、工事管理(施工管理)とは違い、現場において作業員への指示や工事の進捗管理が主な仕事になります。常に現場にたってリーダー的な役割を持っていることが多いです。



ややこしいですが、企業によって工事管理(施工管理)を現場監督と呼ぶケースがあるので明確な線引きはないとされているのが現実です。
工事管理(施工管理)の主な仕事内容
- 施工計画:工事のスケジュールや進行方法を計画する。
- 品質管理:施工が計画通りの品質で行われているかをチェックする。
- 工程管理:工事が予定通りに進行しているかを確認し、遅れがあれば調整する。
- 安全管理:作業員の安全を確保し、事故防止策を実施する。
- 予算管理:工事費用を予算内で管理し、コストオーバーを防ぐ。
このほかにも、書類作成・役所への手続きなどの事務仕事や、設計者や業者との打ち合わせなど幅広い業務を担っています。
工事管理(施工管理)になるために必要な資格や経験
工事管理(施工管理)を担当するためには「施工管理技士」の資格が必要とされています。施工管理技士の資格は下記の7種類に分類されています。
- 資格
- 建築施工管理技士
- 土木施工管理技士
- 電気工事施工管理技士
- 管工事施工管理技士
- 造園施工管理技士
- 建設機械施工技士
- 電気通信施工管理技士
- 実務経験の具体例
- 現場経験:施工現場での実務経験が重要です。一般的には、数年間の現場経験が必要とされます。
- 技術知識:建設技術や工法に関する深い知識が求められます。
- 管理能力:現場管理、技術者の統率、安全管理の経験が必要です。
施工管理技士の資格は、2級の場合、1次試験は17歳以上であれば誰でも受験可能となっており、1次試験合格後、実務経験3年、1級の場合、1次試験は19歳以上であれば誰でも受験可能となっており、1次試験合格後、特定実務経験3年以上が必要です。特定実務経験とは請負代金4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)の工事において、監理技術者・主任技術者の指導の下、または自ら監理技術者・主任技術者として行った経験のことです。



施工管理の受験資格は、令和6年度試験から変更されました。
工事監理とは
工事監理とは、主に建築主(依頼主)や設計者の立場から、工事が設計図書や契約通りに実施されているかを確認・指導することで、欠陥の発生を未然に防ぐ重要な役割を担っています。


さらに、特定の建築物の工事監理は建築士の独占業務であり、資格者としての責務を負っています。
建築士の資格を有していなくてもできる工事監理の建築物は下記の通りです。
| 建築物の用途および構造 | 建築物の延床面積および高さ |
|---|---|
| 木造 | 延床面積:100㎡以下 階数:2階以下 |
| 鉄筋コンクリート造 鉄骨造 石造 煉瓦造 コンクリートブロック造 無筋コンクリート造 | 延床面積:30㎡以下 階数:2階以下 |
工事監理の主な仕事内容
- 設計図書の確認:施工が設計図書や契約通りに行われているかをチェックする。
- 工事の進捗確認:定期的に現場を巡回し、工事の進行状況を確認する。
- 品質確認:工事が所定の品質で進められているかを確認する。
- 問題点の指摘と修正指示:施工上の問題点を指摘し、必要に応じて修正指示を行う。
- 竣工検査:完成後の建物が設計通りに仕上がっているかを最終確認する。
他にも、鉄筋の配筋検査やコンクリート打設時などの要所となる工事に立会い、施工会社からのヒアリングや材料品質証明書・検査結果報告書などの書類確認、写真確認などを行います。また、建設会社からの工事変更要望などに対して、建築主との調整や工期の調整なども行うことで、工事の円滑化を図っています。
工事監理になるために必要な資格や経験
特定の建築物を工事監理する場合、一級建築士・二級建築士・木造建築士を工事監理者として定めなければならないとされています。
- 資格
- 一級建築士
- 二級建築士
- 木造建築士
- 実務経験の具体例
- 設計経験:設計事務所や建設会社での設計経験が重要であり、設計図書の作成および施工現場での監理経験が必要です。
- 法規・基準の知識:建築基準法や関連する法規に精通し、適用する能力が求められます。
- 品質管理経験:施工品質の確認や問題点の是正指示に関する経験が必要です。
工事監理を目指す場合、国家試験の受験要件は学歴のみで、合格後に実務経験の要件を満たせば免許登録できます。建物関係の学歴がない方でも7年間の実務経験を積んで二級建築士を受験する方法もあります。二級建築士としてさらに4年の経験を積めば、一級建築士も目指すことができます。
「工事かんり」呼び方を分ける理由は?
「工事管理(施工管理)」と「工事監理」の呼び方を分ける理由は、工事現場における役割と責任の明確化が目的です。
役割の明確化
工事管理(施工管理)と工事監理は、それぞれ異なる役割を持つため、呼び方を分けることで誰がどの業務を担当するかを明確にします。
- 工事管理:施工者が自社の責任で施工計画を立て、進捗管理、品質管理、安全管理を行う。
- 工事監理:設計者や施主が施工者の工事を監督し、設計図書通りに進行しているか、品質が確保されているかを確認する。
責任範囲の区分
異なる責任範囲を明確にすることで、問題が発生した際にどこに責任があるのかを明確にします。
- 工事管理:施工者が施工全般の進行や安全、コスト管理に責任を持ちます。
- 工事監理:設計者や施主が施工内容が契約や設計図書に適合しているかを確認し、必要に応じて指導・是正を行います。
専門知識の適用
異なる役割には異なる専門知識が必要です。
工事現場のスムーズな進行
呼び方を分けることで、各役割が求める業務の内容や進め方が明確になり、工事現場がスムーズに進行します。これにより、以下のようなメリットがあります。
- 効率的な進捗管理:施工者が効率的に施工を進めるための具体的な管理が可能です。
- 品質と規格の保証:設計者や施主が工事の品質や規格を保証するための監督が可能です。
工事管理(施工管理)と工事監理の担当者には、それぞれ異なる資格や経験が求められます。工事管理(施工管理)では施工技術や現場管理のスキルが重視され、工事監理では設計や法規に関する知識と経験が求められます。
法的・契約上の要件
法律や契約書では、各役割を明確に定義することが求められる場合があります。これにより、各当事者がその責任範囲を理解し、適切に履行することが期待されます。
- 工事管理:施工者は、契約通りに工事を完了させる義務があります。
- 工事監理:設計者や施主は、工事が契約や設計図書に適合しているかを確認する義務があります。
工事管理と工事監理を効果的に行うには?
法規制、契約管理、コミュニケーション、リスク管理、技術の進化への対応など、幅広い知識とスキルが必要です。これらを理解し、実践することで、建設工事を成功へ導くことができます。
まとめ
「工事管理」と「工事監理」の呼び方を分ける理由は、それぞれの役割と責任を明確に区別することで、建設工事の効率的な進行と品質確保を図るためでもあります。これにより、各関係者が自身の業務に専念し、適切に協力し合うことが可能とされています。
さらに、今回の記事で解説させていただいた「工事管理(施工管理)」および「工事監理」以外にも「監理技術者」や「現場代理人」「監督員」などさまざまな役割を持った人が工事に携わっています。
下記の記事では、さらに多くの役割の違いについて解説していますので、お時間ある方はぜひご一読ください。


建設業許可、経営事項審査等の申請手続きや建設業法令に関するご相談がございましたら、あやなみ行政書士事務所へご相談ください。
- スマートフォンの場合は以下の電話番号ボタンのタップで電話がつながります。
- お問い合わせ内容により、有料相談(30分5,500円)となる場合がございます。
- ご相談前に、会社名・担当者名等をお伺いいたします。